玉川上水南側地区の地区計画を改めて考える
GLP計画の説明会が開催される前に、今一度地区計画について考えておく必要があると思い整理をしてみたいと思います。少し長くなりますが、ご覧いただければ幸いです。
1. 影響を受ける範囲
GLPが前回影響を受ける範囲を計画地から500mの範囲として説明会の案内を行ったと説明しましたので、改めて計画地から500mの範囲を、Google Mapに重ねてみました。
赤の破線が計画地から400m、青の破線が500mを表しています。
但しこの範囲が影響を受ける範囲なのかと言えばとんでもありません。昭島市内には大渋滞を引き起しますが、昭島市内に止まらず、立川市、武蔵村山市、八王子市の要所にも影響を与えるものと思われます。
GLPが影響を与える範囲だと言っているのですから、昭島市は地区計画の策定にあたり昭島市民の意見を聴くだけではなく、次の点に配慮した地区計画策定を進めるべきではないでしょうか。
① 地区計画の範囲は影響を受ける範囲に拡大すべき
今回のように東京ドーム13個分という広さの開発行為が周辺の地域に大きな影響を与えるにもかかわらず開発に伴う地区計画の策定にあたっては地権者を中心に決めるため、影響を受ける範囲の住民の権利がないがしろにされようとしています。
既に玉川上水北側地区(西部立川駅南側)や、つつじが丘団地など、個々の地区計画が既に策定されているからと言っても、相互に影響を与え合うのですから、全てを見直すべきと考えます。
② 昭島市は市民の意見を計画に反映すべき
玉川上水南側地区の懇談会に係る意見募集があったが、その意見のまとめが市のホームページで公開されました。ただおかしいなと思うのは会場で質問を行ったり市長への手紙を出したりしましたが、その内容は反映されていないように思います。
「玉川上水南側地区のまちづくりの基本的な考え方についての主な意見」
https://www.city.akishima.lg.jp/s094/010/010/010/kondankaiiken.pdf
市はこの出された意見に対し都市計画に
a) どのように反映しているのか
b) 反映していないのであれば、それは何故なのか。
ハッキリとした市の判断を明確に出すべきでしょう。
都市計画を進めるうえで地権者の同意が必要だということはある程度までは理解を示しても良いですが、市民の生活・市民の意見をないがしろにして言い訳が無いだろうと思います。
③ 市道の整備計画を併せて公表すべき
GLPのトラックは片側1車線の市道を中心に走行しますが、それに伴う市道の整備計画を含め、次の内容を市は同時に公表しなければ、GLPがどのような説明をしても了解できるものではありません。
a) 道路の補修状況の調査と修繕費用の公表が必要
既にひび割れている道路を散見しますので修理が必要です。然しながらGLPが進出してこなければ早急な予算の費消は必要ないのかもしれません。
l
現在の道路で問題のあるところを明確にし
l
いつまでに整備し
l
費用はどの程度必要と考えているのか
l
市税で賄わなければいけないものはどこまでなのか
l
ある程度はGLPに負担させる必要があるのではないかと思えるとことはどこか
b) 新設道路の問題
新設道路はやがて市に提供されると思いますが、その後のメンテナンスなどは市の税金で賄わなければならなくなります。 道路をメインに使うのはGLP なのですから、市は提供を受けないでメンテナンスなどの問題を含め指導を行い、GLPに費用負担させるべきではないかと考えますがそのようにできないのでしょうか。
c) 道路の混雑対策内容の事前公表
既に道路の整備計画の考え方は市に対し出されているのではないでしょうか。となれば、市が整備を行う事業ですから、事前に検討内容の説明をするべきだと思います。
ただ、まだGLPの計画が決まっていないからと言って言及は避けると思いますが、決まってから整備に市税を投入するのは納得がいきません。
道路関係については、他にも多くの市民のみなさんの意見が有ると思います。
私自身、いくつか市長への手紙を出したりしていますので、頂いた回答などを別途公表し考えを共有していきたいと思います。
④ 昭島市は動的シミュレーションを導入するべき
本年、昭島市が交通量調査を行いましたが、市の委員会では、実施したことに対して「実態がわかってよかった」の一言の報告でした。
私は公表された資料を拝見し、失礼ながら調査を行ったことが何に役立っているのか全く分かりませんでした。GLPが進出し交通量が増えることへの不安を皆が訴えているからこそ行った調査のはずではなかったのでしょうか。それを「実態がわかってよかった」の一言では、我々が納めている税金を有効に使って下さっていると私には到底思えません。
また、動的シミュレーションについても同じく、昭島市は一切アナウンスをしていません。
何故、市民が理解しやすいと思う動的シミュレーションを行わせないのでしょう。
事業者がかたくなに拒むのであれば、私はこのことにこそ市税を投じて実施してもらっても良いと思います。
そしてそこからあぶり出される問題を事業者にぶつけ対策を求める、これこそ市民に寄り添う市政と言えるのではないでしょうか。
動的シミュレーションの必要性を下記の流れで説明していますので、ご覧下さい。
a) GLPの交通量事前予測についての一考
https://ikoi-akishima.blogspot.com/2023/09/glp_23.html
b) GLPの交通シミュレーション手法について考える_1
https://ikoi-akishima.blogspot.com/2023/09/glp_26.html
c) GLPの交通シミュレーション手法について考える_2
https://ikoi-akishima.blogspot.com/2023/09/glp_27.html
d) GLPの交通シミュレーション手法について考える_3
https://ikoi-akishima.blogspot.com/2023/10/glp.html
e) GLPの交通シミュレーション手法について考える_4
https://ikoi-akishima.blogspot.com/2023/10/glp4.html
3. 景観上の問題(玉川上水北側から)
景観上の問題について、市は何故GLPの方向性に賛同するような見解を示すのでしょう。特に玉川上水北側の住民の方には最悪です。
今は富士山が見えるのに見えなくなる。この地を終の棲家として長く住んできた人の権利を市はどのように守ってくれるのか? はなはだ疑問です。
何故なら、景観条例に掲載されたイメージへの解釈で、こんな解釈がまかり通るのかという疑問です。
景観条例の挿絵は、遠くに山野を眺望し、そこに見える空をスカイラインとしています。その為の制限として、「玉川上水景観基本軸」の中で建物の高さや規模に関し下記の「景観形成基準」を設けています。
Ø 高さは、周辺建築物群のスカイラインとの調和を図り、著しく突出した高さの建築物は避ける。
特に、玉川上水や緑道の樹木と隣接する敷地では、玉川上水や緑道に面する建築物の高さが、玉川上水や緑道の樹木の最高高さを超えないよう工夫する。
Ø 玉川上水沿いの散策路や周辺の主要な眺望点(道路・河川・公園など)からの見え方に配慮した規模とする
Ø そしてその範囲は玉川上水の中心から左右100mの範囲と定めています。
この図を見た時の印象は、しっかりと景観を守ろうという意志を条例に感じました。
しかし市の解釈は違います。都の担当者にも確認し問題が無いと言われたと言い「都庁の担当者」に責任転嫁をしているように感じます。無理な解釈を持ち込まず、最初から条例を正面から見て、市民に寄り添う姿勢を示してもらいたいと思います。
「開発前の時点で遠くに見える山野とそのスカイラインを考慮もしないで対岸の木を眺め、その延長線上に建物が入れば良い」とする市の解釈をどう考えますか?
懇談会ではその眺望点をどこに置くのかと聞きましたがしっかりとは答えませんでした。
この考え方には、玉川上水北側の住民皆さんへ寄り添う気持ちは微塵もないように思います。
4. 景観上の問題(つつじが丘団地側から)
つつじが丘ハイツ23号棟~25号棟にお住いの皆さんも大変です。下の絵は、つつじが丘ハイツ北側、立木とグリーンしか見えないゴルフ場だったところに、いきなり45mの高さの建物が建てられます。
団地が南側なので、日影などの影響を受けることにはならないのかもしれませんが、今までに無かった建物が壁のように目の前にそびえ立ち視界を遮ることになります。
その高さの違いは、つつじが丘団地 側方からイメージした図をご覧いただけば、どの程度のものになるのかご理解いただけるのではないでしょうか。
5. GLPはごまかすためのデータではなく本当の情報を提供してください。
GLPが説明会で提供した資料をお持ちの方はP24をご覧ください。
お持ちでない方は下記リンクから表示されるデータP21をご覧ください。
(この資料作成時点では見ることが可能でした)
https://drive.google.com/file/d/1ap5bbNhcB126H3iWyx1nqkGcWAbfDGV-/view?usp=drive_link
その図と同じような角度で作成してみました。
実際に提供された図は著作権を主張していますので資料として提示できませんが、建物は白と水色のような建物で表現されているので、真ん中の物流施設は55mもありますが、奥にあるデータセンターよりも低く感じます。実際の提供された絵では、横の代官山緑地の木々の方が高く見えます。
この様に一番圧迫感のない角度を選び、我々に情報を公開していますので、人によっては圧迫感が無くきれいだなという印象を受けた方もおられるでしょう。
ところが少し角度を変えると下図のように見えます。
我々市民がこのような絵を描くのではなく、色々な角度から見ることができるWEB資料を提供するのが筋ではないでしょうか。 公表できない理由が何か有るのでしょうか?
6. 突風などの問題
今までに緑しかなかった場所がコンクリートとアスファルトに埋め尽くされることになります。
特に今まではゴルフ場の芝への散水もあったと思いますが、それのおかげでアスファルトジャングルほどには地熱は上昇せず逆に涼しい風が玉川上水から吹き抜けていたのではないでしょうか。
ところが今まで昭島には無かった高さの建物が林立し、コンクリートとアスファルトで埋め尽くされるとどうなるのでしょう。
地熱が上昇し舞い上がる熱波がどのような影響を及ぼすのか分かりません。
急に吹き抜けるビル風が玉川上水の側道を吹き抜けた時に、歩いていた高齢者や自転車で走行中の子供達が転んだりしないのでしょうか。
リスクマネジメントの観点からもシミュレーションを行うことはできるのではないかと思いますがGLPは実施しないと聞いています。
昭島市役所が都市計画懇談会で提供した資料に建物高さが書いてありませんでしたので、参考に書き込んでみました。
これだけ大きな建物が林立するのですから舞い上がる熱波とビル風などに対する判断をGLPは一向に示そうとしていませんが、昭島市から懇談会の意見を受けて市から説明やコメントが有ってもいいのではないでしょうか。もし本当に事故やケガがあった場合の補償は誰がするのでしょう?
7. 建設土壌と汚染、地下水への影響が心配です
建設土壌と汚染、地下水への影響については「GLP建設工事の安全性は果たして?」というブログで書いていますが、そこで書ききれていなかった部分の補足をしておきたいと思います。
https://ikoi-akishima.blogspot.com/2023/10/glp_28.html
計画地周辺で要措置区域は20ヶ所あり、1ヵ所以外はすべて指定解除となっていると同時に今回の計画地に要措置区域が見られない状況を図にて示していました。
下図はその内容をGoogle Mapに書き写したものです。
原本をご覧になりたい方は、現在も東京都の環境影響審議会の資料「環境影響評価調査報告書」(下記リンク)で表示される資料の77~78ページをご確認ください。
https://assess-toshokohyo.metro.tokyo.lg.jp/uploads/web_public/384_glp-akishima/00/00202238403.pdf
しかしながら下記のようなことが言えるのではないでしょうか。
「環境影響評価調査報告書」の中で公表している計画地近辺の昭島市の土壌汚染の要措置区域の指定を受けた一覧とその場所については、下記の疑問があります。
① 周辺で要措置区域に指定されている地区は、全て同じ企業が所有していた土地で、この計画地だけが何もないというのはおかしいのではないでしょうか。
調べてみると、要措置区域の指定は一番古いもので2004年となっています。土壌汚染の調査を行った時には既に昭和の森ゴルフ場が1969年に開設され調査対象になっていなかった為に要措置区域に指定されていない可能性があります。
② 計画地の用途は、元は飛行場や整備工場であり、当時の軍関連の施設です。
周辺で指定を受けた地域と用途を同じくする土地であり、上記にも記載しましたが土壌汚染を受けている可能性があることが予測される土地です。
③ ゴルフ場に於けるコース造成時の問題並びに運営時の問題は無いでしょうか。
下記の点が検証されなければいけないのではないでしょうか。
a) 計画地では、ゴルフ場建設時に何が埋め立てられたのかもわからない。
b) 長年ゴルフ場の維持管理に除草剤などの薬剤散布もあったと思われますがその影響を考慮しなくて良いのか。
改めて昭島市役所にお願いです。
昭島市は水道事業に影響が出ないことを科学的に検証するよう関係機関と確認してください
8. データセンターの安全確保について
データセンターについては色々な心配があります。
DCは大型コンピューターなどの温度上昇を防御するため冷却のための空調が24時間稼働します。そのため室外機などの騒音問題が心配で、懇談会などでも色々と質問が出ていましたが、市側からは安心しろ、そんな大きな音が出ないような対策がなされているようだなど、安心材料につながる話は一切ありません。私は特に心配なのは、停電発生時に緊急稼働するための発電用の燃料の貯蔵タンクの問題です。
① DCには一般的に停電が発生した時の対策として非常用電源以外に重油などを使った自家発電設備などが必要のようですが、その様な設備や重油等の多量の燃料保管の公表はありません。
周辺に住宅地を控えており、万一の事故を想定した安全対策など、地域へのリスクコミュニケーションが必要です。
②
住宅地のど真ん中に大量の重油かガスなどを貯蔵して安心してくださいと言われて済む問題では有りません。
「これに対する安心は企業が保証するのではなく危険物を保管しているという観点から市がしっかりと検証する責任があるのではないでしょうか」と市長への手紙で質問しましたが、市からは「危険物の保管については、消防法に基づき消防署への手続きが必要と認識しています。」との回答でした。
しかしながら、消防法に基づく消防署への手続きは、住民に告知せず行うのではないでしょうか。そして手続きが済めば住民への告知はせずに、若し問われても消防署に届出て受理されているというのではないでしょうか。
③
自家発電用の設備は、稼働時にとても大きな音が出るという柏市の施設での報告があります。
稼働は停電時のみならず定期的な稼働試験もあり、とても大きな騒音が発生すると共に燃焼の煙と臭いが発生するようですが、GLPからは一切それに関する報告はありません。市はそれを確認し、市民に報告をするつもりは無いのでしょうか。
④
GLP計画地には立川断層直下型地震発生時に震度7となる場所があります。
関東大震災100年の節目に「防災講演会」があり、配布頂いた資料の中に「立川断層帯地震の震度分布」を見るとそこに震度7となる場所がありました。
震度7は地震における最高震度ですが、この震度でも十分に耐えうると宣言頂かなければ、どのような2次災害につながるのかが分からないのではないでしょうか。
GLP計画と立川断層直下型地震発生時の問題というタイトルでブログにも公開しています。
色々と問題点を列挙してきましたが、他にも代官山緑地に生息する動物たちの問題もあれば、玉川上水を中心とした植生への問題などもあります。
そして今GLPが説明会を進める交通渋滞に係る問題があります。
色々と問題点をあぶり出し、情報の共有化も必要と思います。
過去に市長への手紙を出された方はどのような質問をして、どのような回答を得たのか、整理をしてみませんか。私も内容をホームページなどで公開し、お読みいただく皆様と情報共有を進めたいと思っています。
ところで、GLPは配布資料に著作権があると主張し引用を避けるようにと言っているため、資料作成にあたり自前で図の作成をしなければ分かりやすい説明資料が作れません。本当に真剣に市民と会話をしようとするなら、一方的な情報の押し付けではなく、資料に著作権など設定せず自由な会話ができるようにしてもらいたいものです。
また市役所も市民に地区計画を最終的に押し付けるのであれば、この押し付けるという言い方は問題発言かもしれませんが、要は影響を受ける人たちは意見を言っても計画に反映してもらえず、集会が不満を唱える市民のガス抜きに使われてしまっていると共に、地区計画の決定権が無いことによります。
最初に書いたように、甚大な影響を受ける市民:計画地から500m範囲の住民の住まう地域の都市計画を今一度やり直すつもりで、一帯が調和のとれた街づくりを進めるべきではないかと、強く思います。
我々市民は「市長への手紙」を通して市への意見、市への要望を出すことで少しでもGLP計画が改善されるように働き掛けましょう。
守るべきは「市民生活」であり、「子供たちの命」「高齢者の命」です
**********************************************
市長への手紙を書きましょう。
下記のリンクから直接送ることができます。
https://www.city.akishima.lg.jp/form/002/001.html
**********************************************
















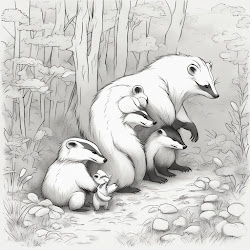
コメント
コメントを投稿