昭島市玉川上水南側地区の地区計画説明会の問題_2
2. 運送用の車両台数を市が把握していない_Ⅱ
GLPの説明は大きな誤解を与えている
GLPが8時台の乗用車の構成比を52.8%と説明しているため、市は乗用車の数量は普通車4,700台の約半分との認識だった。この誤解に基づき車の渋滞などの問題の検討をしているとすれば大きな問題だ。改めて発生交通量と運送用車両の台数について書いておく。
(1) 運送用車両の数
① GLPの発表数量
一日の発生交通量が5800台(大型車約1,100台/日、普通車約4,700台/日)
② 運送用車両の台数:予測
台数の予測は普通車に含まれる乗用車の割合が20%~30%とのGLP発表に基づきます。
普通車と称する4700台は、通勤用乗用車が940台~1400台で、2t車、4t車のような運送用車両が、3300台~3760台含まれると予測されます。
大型車1,100台と合わせると4,400台~4,860台のトラック類が増えることになります。
③ 大型車と普通車の寸法のイメージ
大型車は5t以上、普通車は5t未満で区別するとのことでしたが、各サイズの概要は下記の通りです(WEB調べ:メーカーにより異なるようで、概略として見て下さい)
大型車 12t 長さ:12m以内
大型車 8t 長さ:8.4~11m
普通車 4tロング 長さ:7.2m~8.6m
普通車 4t 長さ:6.2m
普通車 2tロング 長さ:5~6m程度
普通車 2t 長さ:4.7m
普通車 乗用車(3ナンバー) 長さ:4.7m
④ GLP説明の大型車と普通車の違い
GLPは説明の中で、大型車はタイヤが3軸で、普通車は2軸と言っていますが、この区分方法はいいかげんです。昭島市内でナンバープレートは大型標板で、且つ自動車の種類と用途を示した番号が100番台、且つ最大積載量が7100kgと記載されたトラックは2軸の車両でした。
4tロングは大きく、上記寸法でもわかるように8tトラックとほぼ同じような寸法ですが、これも普通車として一般道路を走ることになります。
宅配便企業のトラックをよく見かけますが、2t・4t車両中心で、中にはかなり大きく感じる車もありますが、そこかしこ走ることになります。
⑤ 大型車の走行ルートと普通車の走行ルート
普通車は新設道路の南側(はなみずき通りからつつじが丘通りまで)とつつじが丘通り交差点までを走行できることになりますが、その中には2t・4tロングの車両までが普通車と称して走行が可能になります。
⑥ 渋滞に大きな影響を与える:GLPの発表は信用できないのでは?
GLP発表の需要率は高くても0.6~0.7で渋滞は発生しないとの発表でしたが、専門家を自称するGLPのアドバイザーは信用に値しないのではないでしょうか。
何故なら、現実的に渋滞している箇所が散見される事実がありながら、これ以上に車が増えても渋滞しないと言うのですから信用できません。
「静的シミュレーションは1時間の交差点単位の交差点需要率に基づき計算するので、1時間中には粗密が有り通れる時間と通れない時間が発生する可能性がありますが」のようなニュアンスの後に、「渋滞はしないと思います。」と言いました。思いますと言う頼りない言葉に子供達の命を預けることはできません。
(2) 動的シミュレーションについて
GLPは交通量調査に於いて静的手法を用いるとのことでしたが、昭島市に於いても市は動的手法による検証は行わないと共に、その裏付けとして大店立地法では東京都は静的手法を採用しており問題ないとの議会説明でした。
然しながら、施設の規模を考えた場合、埼玉県や多くの他府県では動的手法の採用を推奨するレベルであり、「重要物流道路に於ける交通アセスメント」という面から考えても巨大な施設で動的手法を採用すべきレベルと考えます。
当該計画地は重要物流道路沿いではありませんが、幹線道路である重要物流道路でも問題になる規模であるにもかかわらず、片道1車線の市道中心の運行を考えると、より渋滞被害は大きくなることが想定されます。
この道路アセスの規定では、道路管理者が特に必要と認める施設については動的手法を採用すべきとしております。
また、静的手法は規模が大きくなると時々刻々と変化する交通状況や周辺交差点への影響などを考慮できないという短所がある半面、動的手法は時々刻々と変化する交通状況の把握には向いており、複数の交差点間の信号制御や周辺の踏切などの条件も加味したシミュレーションが可能であるなど、分かり易くて正確な判断を導き出すのに向いています。
この問題につきましては、「市長への手紙:GLP採用の静的手法に関して」でも触れていますのでご確認ください。
https://ikoi-akishima.blogspot.com/2023/12/glp_16.html
-以上-
昭島市もこのような市民の希望を叶えるための努力を遂行してもらいたいと思います。
と同時に、我々市民は「市長への手紙」を通して市への意見、市への要望を出すことで少しでもGLP計画が改善されるように働き掛けましょう。
守るべきは「市民生活」であり、「子供たちの命」「高齢者の命」なのですから。
**********************************************
市長への手紙を書きましょう。
下記のリンクから直接送ることができます。
https://www.city.akishima.lg.jp/form/002/001.html
**********************************************





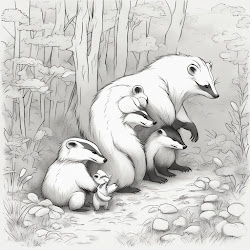
コメント
コメントを投稿